こんにちは、ハムスター社長です🐹
今日は税金のお話です。
税金の中でも特にややこしい所得税。
この所得税の基本知識を紹介していきたいと思います。
この記事が参考になる人
- 所得税について知りたい人
- 確定申告を行うけど、税金の知識があまりない人
はい、目次!!
所得税とは?
所得税とは、個人が1年間(1月1日~12月31日)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額を所得といい、この所得に対してかかる税金のことです。
所得税の納税義務者と納税範囲
所得税法によって、納税義務者は納税範囲が決められています。
所得税の納税義務者
まず納税義務者は、
| 居住者 | 日本国内に住所があるかまたは現在まで引き続いて1年以上居所がある個人。 |
| 非居住者 | 居住者以外のもの。 |
に分けられます。
さらに、居住者は
| 非永住者以外の居住者 | 居住者のうちで非永住者に該当しないもの。 |
| 非永住者 | 居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所または居所を有する期間の合計が5年以下である人。 |
に分けられます。
非永住者以外の居住者は、国内および国外で生じたすべての所得に対して所得税が課税されます。
非永住者や非居住者は、課税の範囲が狭くなります。
所得税の納税範囲
納税義務者の区分によって、課税の範囲が変わります。
| 納税者義務者の区分 | 課税の範囲 | |
| 居住者 | 非永住者以外の住居者 | 国の内外で生じたすべての所得 |
| 非永住者 | 国内において生じた所得(国内源泉所得)と これ以外の所得(国外源泉所得)で 日本国内において支払われたもの又は 日本国内に送金されたもの | |
| 非居住者 | 日本国内において生じた所得(国内源泉所得) | |
所得税がかからないもの(非課税のもの)
次のものには、所得税がかかりません。
【所得税がかからないもの(非課税のもの)】
- 社会保険の給付金
- 通勤手当(月15万円まで)
- 生活用動産(※)の譲渡による所得
- 損害または生命保険契約の保険金で身体の傷害に起因して支払われるもの
- 損害保険契約の保険金で資産の損害に起因して支払われるもの
※30万円超の貴金属などを除く
社会保険の給付金には、以下のようなものがあります。
【社会保険の給付金の例】
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 埋葬料
- 出産育児一時金
厳密言うとこれらは、社会保険の一部である医療保険による給付金です。
社会保険の基本について知りたい方は、下記を参考に!

所得税の分類
所得税は、誰が課税するのかによって下記に分かれます。
- 国税(国が課税するもの)
- 地方税(地方公共団体が課税するもの)
また、税金を直接納めるか、間接的に納めるかによって下記に分かれます。
- 直接税
- 間接税
いくつかの税金を1つの表に分類分けするとこんな感じです。
| 直接税 | 間接税 | |
| 国税 | 所得税 法人税 相続税 贈与税 | 消費税 印紙税 酒税 |
| 地方税 | 住民税 事業税 固定資産税 | 地方消費税 |
所得税の納税方式
納税方式は、下記によって分類されます。
| 意味 | 例 | |
| 申告納税方式 | 納税者が自分で納税額を計算して申告。 | 所得税 法人税 相続税 |
| 賦課課税方式 | 国や地方公共団体が納税額を計算して納税者に通知。 | 住民税 固定資産税 |
固定資産税は、住宅・土地を持っている人が支払う税金です。
固定資産税について知りたい方は、下記を参考に!

所得税の総合課税と分離課税
所得税の税額計算は下記5つの流れで行います。
【所得税の計算の流れ】
- 所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を計算する。
- 各所得金額を合算して、課税標準を計算する。
- 課税標準から所得控除を差し引いて、課税所得金額を計算する。
- 課税所得金額に税率をかけて、所得税額を計算する。
- 所得税額から税額控除を差し引いて、申告税額を計算する。
①で「所得を10種類に分ける」とあります。
10種類の所得を見てみましょう。
最終的な申告税額を求めるときに、所得を10種類に分けたら、
各所得金額を合算する総合課税と、各所得金額を分離する分離課税に分けて課税標準を求めます。
総合課税
総合課税に分類される所得は、次のものがあります。
【総合課税に分類される所得】
- 利子所得(国内で源泉徴収されないもの)
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得(土地、建物、株式等の譲渡所得以外)
- 一時所得
- 雑所得
分離課税
分離課税に分類される所得は、次のものがあります。
【分離課税に分類される所得】
- 利子所得(国内で源泉徴収されないもの以外)
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得)
利子所得・譲渡所得は、場合によって総合課税と分離課税どちらにもなり得るので注意が必要です!
また分離課税には、
| 申告分離課税 | 所得を得た人が自分で税額を申告するタイプの分離課税。 |
| 源泉分離課税 | 所得から税額が天引きされるタイプの分離課税。 |
があります。
所得税の申告
所得税の申告方法は2つあります。
があります。
1つずつ紹介します。
また確定申告には、青色申告、白色申告もありますが、これはまた別の記事に上げます。。。
確定申告
確定申告とは、1年間の所得に対する納税額を計算して申告し、納税する一連の手続きのことです。
また、確定申告の実施時期と対象者は下記です。
| 実施時期 | 2月16月~3月15日 |
| 対象者 | 個人事業主やフリーランスとして働いている人 給与所得が2,000万円を超える人 副業の所得が年間20万円を超える人一定額の公的年金を受け取っている人 株取引で一定の利益を得た人 不動産などそのほかの所得があった人 2ヶ所以上の就業先から一定の収入を得ている人 |
上記の対象者以外に、確定申告をした方が良い人は
- 住宅ローン控除1年目の人
- 年度途中に退職した人
- 医療費控除を適用したい人
- 株式などの譲渡損失によって、損益通算をしたい人
などです。
年末調整
年末調整とは、会社等の給与の支払者が1年間の所得に対する納税額を計算して申告し、納税する一連の手続きのことです。
また、年末調整の実施時期と対象者は下記です。
| 実施時期 | 10月ごろ |
| 対象者 | 会社などに1年を通じて勤務している人 年の中途で就職し年末まで勤務している人 |
会社員は、確定申告しなくていい代わりに、年末調整が必須となってきます。
年末調整は確定申告よりややこしくないので、会社員はこの恩恵を受けていますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事を下記へまとめます。
この記事のまとめ
- 所得税とは、個人が1年間(1月1日~12月31日)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額を所得といい、この所得に対してかかる税金のこと。
- 所得税がかからないもの(非課税のもの)の例は、社会保険の給付金や通勤手当などがある。
- 所得税の分類には、国税と地方税、直接税と間接税がある。
- 所得税の納税方式には、申告納税方式と賦課課税方式がある。
- 所得は10種類あり、総合課税と分離課税に分けられて所得税を計算する。
- 所得税の申告には、確定申告と年末調整がある。
この記事が参考になれば嬉しいです(/・ω・)/
以上、ハムスター社長でした🐹
ブログ村のランキング参加しております♪ もし良ければ、ポチッと押してください!
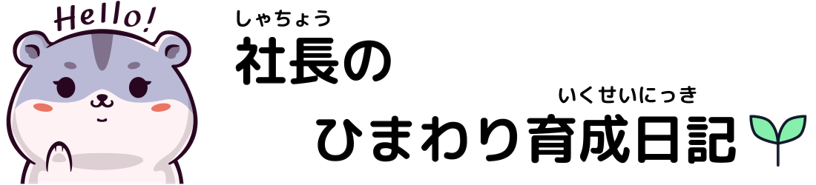
コメント