こんにちは、ハムスター社長です🐹
現在産休中です。
出産準備のために産休取らせてもらっていますが、
なんせ行動はしていたい。
ということで、
だいぶ前に購入していたFP(ファイナンシャルプランナー)の教科書を
引っ張り出してきました。
暇な時間にぺらぺらめくってます。

ぺらぺらめくるんじゃなくて、勉強せえ!
FPの教科書の初めの方に出てくる「社会保険」について、
ややこし~、どこかでアウトプットしたい~、
と思ったので、今回このページにて解説していきたいと思います。
社会保険料とは?

そもそもややこしい社会保険料。
社会保険料は会社員であれば、給料から天引きされているので
意識せずに 搾取されています 徴収してくださいます。(笑)
社会保険料の「そもそも何なの?」を知っていきましょう。
社会保険って何?
そもそも何?って感じですよね。下記で一般的な意味を記載します。
社会保険とは、労働者個人の生活を守るため、生活を脅かす事象が発生した場合、
必要な給付を行う公的保険の総称のことです。
公的保険は、国や自治体が運営しています。
社会保険は、【狭義】と【広義】がある?
社会保険には、広義(ひろーい)と狭義(せまーい)の2つの考え方があります。
下記5つの保険が含まれます。
- 医療保険
- 介護保険
- 年金保険
- 労災保険
- 雇用保険
下記3つの保険が含まれます。
- 医療保険
- 介護保険
- 年金保険
【労働保険】
下記2つの保険が含まれます。
- 労災保険
- 雇用保険
ですが、「社会保険料」を計算するときは、「広義の社会保険」を考えて計算してください。
社会保険料については、後で解説します。
社会保険料の計算方法

社会保険料は下記で計算できます。
= 医療保険料 + 年金保険料 + 介護保険料 + 労災保険料 + 雇用保険料
- 勤務形態(会社員・フリーランス)
- 年齢
- 業種
によって変化するので、さらにややこしく感じます。
医療保険料の計算方法
医療保険には3種類あります。
- 健康保険・・・会社員とその家族が対象
- 国民健康保険・・・自営業者などとその家族が対象
- 後期高齢者医療制度・・・75歳以上の人が対象(※1)
健康保険料の計算方法
= 標準報酬月額(標準賞与額) × 保険料率
保険料率は、ご自身が加入している健康保険組合や協会けんぽのHPで確認できます。
国民健康保険料の計算方法
= 医療分 + 支援金分 + 介護分
市町村区によって課税方法が異なり、
前年の所得などによっても決定されます。
後期高齢者医療制度 保険料の計算方法
= 均等割額 + 所得割額
均等割額、所得割額は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定されます。
詳細はお住いの広域連合HPで確認してください。
年金保険料の計算方法
年金保険には2種類あります。(私的年金は除きます。)
- 国民年金保険・・・20歳以上60歳未満のすべての人が加入
- 厚生年金保険・・・会社員や公務員が加入
国民年金保険料の計算方法
一律 16,520円/月です。(令和5年度)
厚生年金保険料の計算方法
= 標準報酬月額(標準賞与額) × 18.3%
介護保険料の計算方法
介護保険は、40歳以上が加入する保険です。
年齢によって介護保険料が変わります。
- 第1号被保険者・・・65歳以上が対象
- 第2号被保険者(※2)・・・40~65歳以上が対象
※2 個人事業主や未就業者の場合は、計算方法が異なる。
第1号被保険者の介護保険料 計算方法
= 基準額 × 所得別の係数
基準額や、所得別の係数は、市町村区によって異なります。
第2号被保険者の介護保険料 計算方法
= 標準報酬月額(標準賞与額) × 保険料率
保険料率は、ご自身が加入している健康保険組合や協会けんぽのHPで確認できます。
労災保険料の計算方法
労災保険は、事業主が全額負担します。
ですので、会社員・フリーランスは負担しなくていい保険です。
しかし、特別加入制度という任意加入制度もあるので、
労災保険に入りたい方は、一度調べてみてください。
雇用保険料の計算方法
雇用保険は、労働者が失業した時などに、給付を行ったり再就職を援助する保険です。
= 給与額(賞与額)× 保険料率
社会保険の注意点3つ

これまでに解説してきたように、
社会保険は5つの保険から成り立っているので
「よく聞くワードだけど、説明はできない」って方が多いと思います。
そんな社会保険ですが、
よく言われる注意点を3つ厳選したので、ご紹介したいと思います。
会社員は4月~6月に残業すると、社会保険料が高くなる
これが言われている理由は、「標準報酬月額」が係わっているからですね。
※標準報酬月額は、4~6月の給与の平均値で決定されます。
標準報酬月額が係わる保険は、
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
の3つです。この3つは、会社員であれば支払っている保険です。
フリーランスであれば、
・健康保険 → 国民健康保険
・厚生年金保険 → 国民保険
・介護保険 → 国民健康保険の「介護分」
となるので、標準報酬月額は関係ありません。
ですので、会社員で「社会保険料あまり払いたくないよ」って人は、
4~6月の残業を気にして働くことをお勧めいたします!
社会保険の保険料率はちょこちょこ改定される
健康保険料率・介護保険料率がちょこちょこ改定されています。
※上がったり、下がったりは都道府県で異なります。
また、雇用保険率も2022年に引き上げられました。
これは、コロナ渦で雇用保険の支出が増えたためです。
保険料率が変化するたび、ニュースになりますよね。
保険料率があがったら、
私たちの支払う保険料があがってお財布の中がさみしくなりますので、
こういったニュースにもアンテナをはっておくといいでしょう。
最近だと、岸田政権が「異次元の少子化対策」のたたき台を公表しましたよね。
それに伴い、社会保険料もあがると思います。
Yahoo!ニュースにも上がっていますので、参考にご覧ください↓
岸田政権「異次元の少子化対策」財源は社会保険料が本命か 年収600万円の会社員は税金と別に「100万円超の天引き」も(マネーポストWEB) – Yahoo!ニュース
社会保険料における扶養の壁
いくつか「扶養の壁」があるのですが、それはまたおいおい記事にします(/・ω・)/
会社員の配偶者が被扶養者と認められる条件は下記です。
- 年収130万未満であること
- 被保険者の収入金額の2分の1以下であること
ですが、年収130万を超えてしまうと、
厚生年金保険・健康保険に加入する義務が生じてしまうため、
要注意です。
例えば、
年収131万であれば、社会保険料は約19万支払わねばならなくなり、
手取りが約112万になってしまいます。
年収131万の働きをしたのに、112万しかもらえないのであれば、
なんだかやる気がなくなってしまいますよね(笑)
もちろん、厚生年金保険・健康保険の恩恵を受けたいのであれば、
払う価値はあります!
最後に
いかがでしたでしょうか?
何回も見直していますが、ほんとにややこしい社会保険。
いつになったら頭に入ってくれるのでしょうか。
この記事がみなさんのお役に立てれば幸いです(/・ω・)/
以上、ハムスター社長でした🐹
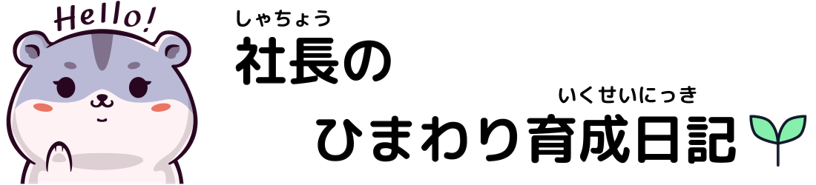
コメント