こんにちは、ハムスター社長です🐹
産休に入ってからもうすぐ3か月経ちそうです。
通常、産休に入ってから1年2か月ほどで職場復帰しますが、
妊娠して体力の低下が著しいので、今のところ職場復帰できる気がしませんw
毎日職場に行って働いてる人は本当にすごいと思います。
(私もフルタイムで働いてたはずなんだけどな…)
なので時々考えるんですよね。
 ハムスター社長
ハムスター社長ってw
完全に仕事辞めたいモードに入っております。
(ま、どーせ仕事は続けるのですがw)
そこで今回は、いつの日か退職金をもらう未来のために、
退職金・退職所得を理解しておこうってことで色々勉強したので
本ページで紹介しておこうと思います。
はい、目次!!
退職所得の基礎知識
まず、退職所得の基礎知識を学んでいきましょう。
退職所得とは?
退職所得とは、退職によって勤務先から受け取る退職金などの所得のことをいいます。
また退職所得は、同期で入った人と比べても勤続年数、退職理由、勤続中の成果評価などによって
人それぞれ異なります。
退職所得の計算方法
退職所得は次の計算式によって決まります。
また勤続年数の換算ですが、1年未満の年がある場合でも1年に切り上げて計算されます。
退職所得控除額は、以下で決まります。
| 勤続年数 | 退職所得控除 |
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
20年以上働いたら、一気に退職所得控除額の幅が広がりますね。
(逆に20年以上もお勤めしなきゃいけないのか( ^ω^)・・・という感じですね)
退職所得の計算例は以下になります。
例:勤続年数35年3か月で退職金が3000万円である人の退職所得金額は?
退職所得控除額
= 800万円 + 70万円 × (36年 - 20年)
= 1920万円
退職所得
= (3000万円 - 1920万円) × 1/2
= 540万円
答え:勤続年数35年3か月で退職金が3000万円である人の退職所得金額は、540万円となる。
以下は、退職金が3000万円のとき、税金がどれだけとられるのか計算した結果です。
気になる人は、見てください。
上記の例でいくと、退職金をもらった年に、その年の収入が退職金しかない場合、
この退職所得金額540万円から所得控除を差し引き、所得税、住民税、復興特別所得税の税率を掛けたら、
その年の税額が求まります。
所得税の税率は、累進課税制度で所得金額によって異なります。
住民税の税率は、一律10%。
復興特別所得税の税率は、一律2.1%。
所得控除については、また別の記事にて書きます。
所得控除が基礎控除(48万円)しかない場合は、
540万円 - 48万円 = 492万円
で、492万円に所得税、住民税、復興特別所得税の税率をかけます。
所得税 55.7万円
住民税 49.2万円
復興特別所得税 10.332万円
となり、退職金が3000万円あっても、税金として約115万円支払わなければならないのです。
退職所得の課税方法
退職所得の課税方法は、分離課税となります。
分離課税とは、他の所得と合算せずに税額を計算する方法です。
他の所得とは、退職所得以外の9種類の以下所得のことです。
それぞれの所得については、個別にまた解説しますので少々お待ちください。
また、「所得」について知りたい方は下記をぜひ参考にしてください。
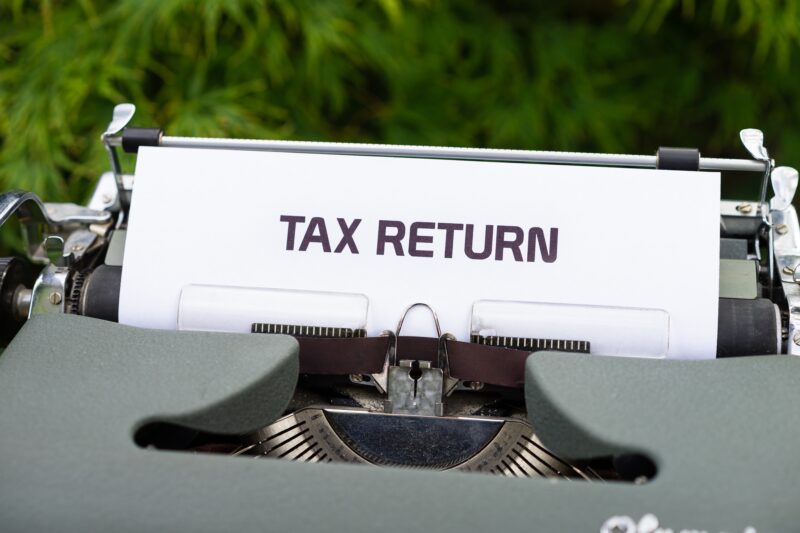
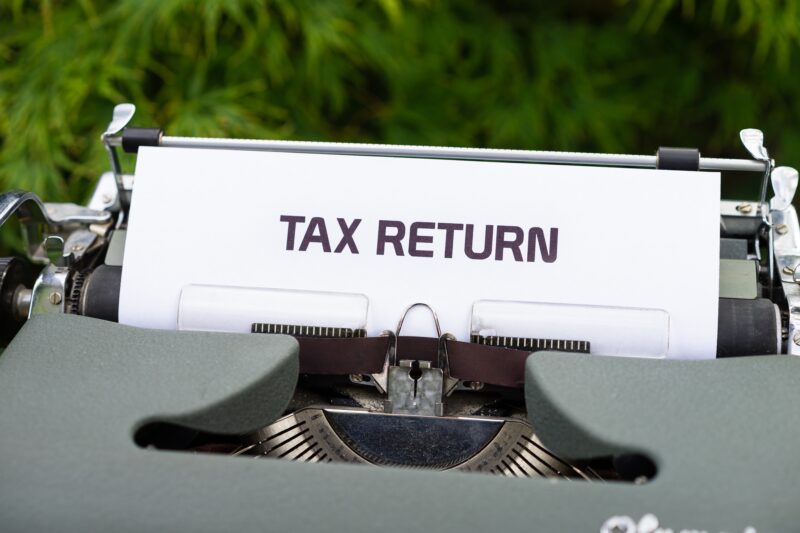
退職金を受け取るときの注意点2つ
退職金を受け取るとき、2つ注意点があります。
【退職金を受け取るときの注意点2つ】
- 退職金の受け取り方法は、一時金と年金の2種類
- 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を忘れずに
以下で紹介していきます。
退職金の受け取り方法は、一時金と年金の2種類
退職金の受け取り方法は、2種類あります。
「一時金」として受け取る場合か、「年金」として受け取る場合の2種類です。
※企業によっては、退職金の一部を「一時金」として多めに受け取り、
その残りを「年金」としてちょっとずつ受け取る場合もあります。
退職金の受け取り方法は、一時金 or 年金どっちがいいの?
なんて声も聞こえてきそうですが、
結論、退職金のお得な受け取り方法は人それぞれによって異なります。
どの場合で年金を受け取った方が良いかは、
人それぞれ異なるので自分で税金シュミレーションしてみるか、FPに相談するのが良いですね。
退職金を「一時金」として受け取る場合
退職金を「一時金」として一括で受け取った場合、退職所得として所得税が課されます。
比較的若い年齢で退職した場合は、退職金も少ないので、
退職金を「一時金」として受け取った方が税金を少しでも抑えれることが多いです。
退職金を「年金」として受け取る場合
退職金を「年金」として分割で受け取った場合、雑所得として所得税が課されます。
退職金を分割でもらうので、お金の使いすぎを防止できますが、
退職所得控除の枠を使用できません。
また、退職と同時に公的年金も一緒にもらう場合は、公的年金も雑所得として課税されるので注意が必要です。
逆に、公的年金の受け取りを繰り下げる(年金受給開始年齢を遅らせること)場合、
雑所得として課せられるのは、「年金」として分割で受け取った場合の退職所得だけになるので、
「年金」として分割で受け取ったら絶対不利というわけでもないです。
ただ、「年金」として分割で受け取った場合は、税金面のことをよーく考えて年金受け取り方法を選択する必要があります。
また、公的年金について知りたい方は下記をぜひ参考にしてください。


「退職所得の受給に関する申告書」の提出を忘れずに
退職所得の受給に関する申告とは、読んで字の如く、退職金をもらったときに勤務先に提出する申告書です。
大半は、勤務先で「退職所得の受給に関する申告」の提出を求められると思いますが、
勤務先が忘れている場合もありますので、ご自身で「退職所得の受給に関する申告」の提出を忘れないように自己管理しましょう。
万が一、「退職所得の受給に関する申告」を提出しなかった場合、
退職金の額に対して一律20.42%の税率が課せられます。
もちろん退職所得控除などが受けられないので、「退職所得の受給に関する申告」を提出しなかった場合は提出した場合より、多めに税金を払っているので要注意です。
この場合、確定申告をすれば払いすぎた税金が戻ってくるので、「退職所得の受給に関する申告」を提出しなかったときは、必ず確定申告するようにしてくださいね。
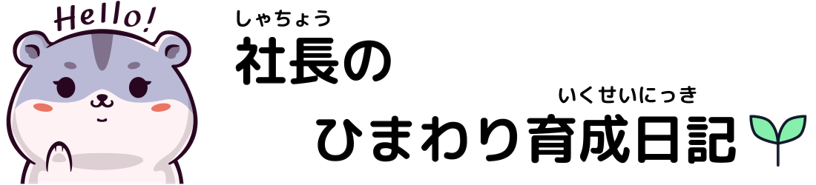
コメント