こんにちは、ハムスター社長です🐹
昨今のコロナ渦で株式投資ブームに火が付きましたね。
徐々にこのブームのほとぼりは冷めていってるようですが、まだまだ熱い株式投資ブーム。
そんな株式投資商品の1つである「NISA」。

なんて考えるてる人も多いはずです。
今回は、そんなNISAの基礎知識について紹介したいと思います。
この記事が参考になる人
- NISAについて知りたい人
- NISAで資産形成を行いたい人
- 投資初心者の人
はい、目次!!
NISAの基本
NISAの基本知識から一緒に学んでいきましょう!
NISAとは?
NISAとは、2014年1月から導入された少額投資非課税制度をいい、証券会社で一般口座、特定口座、NISA口座で分けられます。
「ニーサ」と読みます。
証券会社の一種の口座枠と思ってください。
NISA制度によって開設される口座は、下記3種類があります。
また、2024年から新制度のNISAが始まるので、これも紹介していきます。
一般NISA(現行)
一般NISAの概要は以下です。
| 非課税投資可能額 | 120万円/年 |
| 対象商品 | ・上場株式 ・株式投資信託 ・ETF(上場投資信託) ・REIT(不動産投資信託) など |
| 非課税の期間 | 5年間 |
| 利用できる人 | 日本国内に住んでいる20歳以上の人 |
一般NISAの対象外商品は、下記です。
【一般NISAの対象外商品】
- 預貯金
- 公社債(公債と社債など,諸債券の総称。)
- 公社債投資信託(株式の商品を組み入れていない投資信託のこと。)
2024年から新制度のNISAに代わるので、2024年以降は、一般NISA(現行)の非課税枠は利用することができません。
金融機関の変更(例えば、楽天証券のNISA口座からSBI証券のNISA口座への変更など)は、所定の手続きを行えば、1年間ごとに変更可能です。
つみたてNISA(現行)
つみたてNISAは、一般NISAに比べて長期的に積み立て投資を行うものです。
| 非課税投資可能額 | 40万円/年 |
| 対象商品 | ・長期の積立 ・分散投資に適した一定の投資信託 (信託期間20年以上、非毎月分配型ファンドなど) |
| 非課税の期間 | 20年間 |
| 利用できる人 | 日本国内に住んでいる20歳以上の人 |
一般NISAとつみたてNISAの併用はできません。
2024年から新制度のNISAに代わるので、2024年以降は、つみたてNISA(現行)の非課税枠は利用することができません。
金融機関の変更(例えば、楽天証券のNISA口座からSBI証券のNISA口座への変更など)は、所定の手続きを行えば、1年間ごとに変更可能です。
ジュニアNISA
ジュニアNISAは、未成年者を対象としたNISAです。
| 非課税投資可能額 | 80万円/年 |
| 対象商品 | ・上場株式 ・株式投資信託 ・ETF(上場投資信託) ・REIT(不動産投資信託) など |
| 非課税の期間 | 5年間 |
| 利用できる人 | 日本国内に住んでいる20歳未満の子ども |
ジュニアNISAという名前なので、



と思うかもしれませんが、そういうことではなく、子どもの代わりに親が運用します。
ただ、ジュニアNISAの口座名は、子どもの名義でなければいけません。
2024年から新制度のNISAに代わるので、2024年以降は、ジュニアNISA(現行)の非課税枠は利用することができません。
また、金融機関の変更(例えば、楽天証券のNISA口座からSBI証券のNISA口座への変更など)は、不可能です。
金融機関を変更したい場合は、既存の口座を廃止してから口座を新設しなければいけません。
一般NISA(新制度)
新制度の一般NISAは、現行の一般NISAと比べて、大幅に改善がありました。
| 非課税投資可能額 | 240万円/年(現行NISAから大幅に増額!) |
| 対象商品 | ・上場株式 ・株式投資信託 ・ETF(上場投資信託) ・REIT(不動産投資信託) など |
| 非課税の期間 | 無期限(現行NISAから大幅に期間延長!) |
| 利用できる人 | 日本国内に住んでいる18歳以上の人 (現行NISAから利用できる年齢枠増加!) |



つみたてNISA(新制度)
新制度のつみたてNISAも、現行のつみたてNISAと比べて、大幅に改善がありました。
| 非課税投資可能額 | 120万円/年(現行NISAから大幅に増額!) |
| 対象商品 | ・長期の積立 ・分散投資に適した一定の投資信託 (信託期間20年以上、非毎月分配型ファンドなど) |
| 非課税の期間 | 無期限(現行NISAから大幅に期間延長!) |
| 利用できる人 | 日本国内に住んでいる18歳以上の人 (現行NISAから利用できる年齢枠増加!) |



NISAで注意すること
NISAで注意することをまとめました。
現行NISAから新制度NISAへそのまま移管できない
現行NISAから新制度NISAへ、金融商品を移管することはできません。
現行NISAと新制度NISAは、まったく別の口座になります。
現行NISAで運用していた金融商品を新制度NISAで運用したい場合は、現行NISA+新制度NISAの口座で投資信託の商品を保有していくことになるでしょう。
また、現行NISAの保有期限(一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間)が終了したら、勝手に課税口座(普通口座、特定口座)に移管され、課税されます。
なので、保有期限が終わるまでに現行NISAで保有している金融商品の売却をお勧めします。
NISAで含み損が出た場合、損益通算ができない
NISA口座で含み損、特定口座(普通口座)で利益が出てる場合、NISA口座の損益通算はできません。
損益通算とは、損失と利益を相殺することを言います。
株式投資で損益通算できるのは、上場株式等の譲渡所得と上場株式等の配当所得です。
これに関して知りたい方は、下記を参考に!


新制度NISAの非課税保有限度額1800万円は、買付値ベース
新制度NISAの非課税保有限度額1800万円は、買付値ベースです。
例えば、新制度のNISAで100万円のA社の投資信託を購入したとします。
その場合、その年の新制度NISAの非課税投資可能額は 1800万円 - 100万円 = 1700万円 です。
仮に、年内に購入したA社の投資信託100万円分の株価が上がって200万円になったとします。
この場合、その年の新制度NISAの非課税投資可能額は、1700万円のままです。
新制度NISAの非課税保有限度枠は、再利用可能
新制度NISAの非課税保有限度枠は、再利用可能です。
例えば、新制度のNISAで100万円のA社の投資信託を購入したとします。
そして、そのA社の投資信託100万円分の株価が上がって200万円になり、年内中に全部売却したとします。
この場合、その年の新制度NISAの非課税投資可能額は1700万円ではなく、1800万円に戻ります。
新制度NISAのつみたて枠と一般枠は、別の金融機関で運用できない
新制度NISAでつみたてNISAと一般NISAを併用して運用する場合、別々の金融機関で運用できません。
金融機関の変更(例えば、楽天証券のNISA口座からSBI証券のNISA口座への変更など)は、所定の手続きを行えば、1年間ごとに変更可能です。
NISAに関してよく疑問に思うこと
NISAに関してよく疑問に思うことをまとめました。
運用するなら、NISAとiDeCoどっちがいい?
結論、iDeCoとNISAどっちかしか運用したくないのであれば、
NISAを優先的に運用していくべきです。
まず、iDeCoをさらっとおさらいしましょう。
個人型確定拠出年金=iDeco と言われます。
厚生労働省が「イデコちゃん」というキャラクターまで作って
日本国民にiDeCoの加入を積極的に勧めています。
次に、NISAとiDeCoのメリット・デメリットをまとめてみました。
| NISA | iDeCo | |
| メリット | ・運用益が非課税 ・資金がいつでも引き出せる | ・運用益が非課税 ・積立時の掛金が全額所得控除 |
| デメリット | ・含み損が出ても損益通算できない | ・資金が60歳まで引き出せない ・含み損が出ても損益通算できない |
NISAのデメリットより、iDeCoのデメリットの方が多いですね。
さらに、年間の投資可能額だけで比べると
| つみたてNISA | 一般 NISA | 新制度 NISA | iDeCo | |
| 年間投資可能額 | 40万円 | 120万円 | 1800万円 | 14万4000円〜81万6000円 (職業、加入している年金制度に より異なる) |
新制度NISAとiDeCoを比べると、明らかにNISAの年間投資額が段違いで大きいことがわかりますね。
よって、iDeCoとNISAどっちかしか運用したくないのであれば、NISAを優先的に運用していくことをおすすめします。
iDeCoに関して知りたい方は、下記を参考に!


2023年から始めるなら、つみたてNISAと一般NISAどっちがいい?
結論、2023年度からNISAを始めるのであれば、
- 資産運用に自信がある人 → 一般NISA
- 資産運用に自信がない人 → つみたてNISA
をおすすめします。
上記のおさらいですが、年間投資可能額は下記です。
| つみたてNISA(現行) | 一般NISA(現行) | |
| 年間投資可能額 | 40万円 | 120万円 |
| 非課税保有期間 | 20年間 | 5年間 |
年間投資可能額が大きいのは、一般NISAですが、非課税保有期間が長いのは、つみたてNISAです。
資産運用で利益を出しやすいのは、長期投資です。
なので、非課税保有期間が長いつみたてNISAの方が初心者でも利益を出しやすいのです。
できるだけ失敗したくない!資産運用初心者!の方は、つみたてNISAをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事を下記へまとめます。
この記事のまとめ
- NISAとは、2014年1月から導入された少額投資非課税制度。
- 現行のNISAには、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの3種類ある。
- 新制度のNISAには、一般NISA、つみたてNISAの2種類ある。
- 現行NISAから新制度NISAへそのまま移管できない。
- NISAで含み損が出た場合、損益通算ができない。
- 新制度NISAの非課税保有限度額1800万円は、買付値ベース。
- 新制度NISAの非課税保有限度枠は、再利用可能。
- 新制度NISAのつみたて枠と一般枠は、別の金融機関で運用できない。
- 運用するなら、NISAとiDeCoどっちがいい? NISA!
- 2023年から始めるなら、つみたてNISAと一般NISAどっちがいい?
初心者はつみたてNISA、投資経験者は一般NISA!
この記事が参考になれば嬉しいです(/・ω・)/
以上、ハムスター社長でした🐹
ブログ村のランキング参加しております♪ もし良ければ、ポチッと押してください!
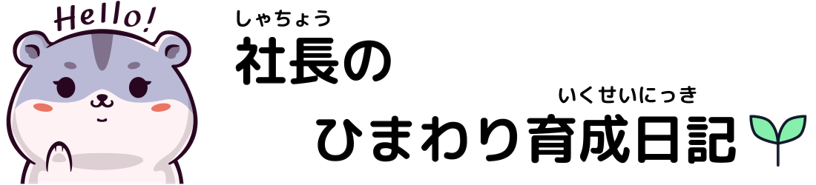
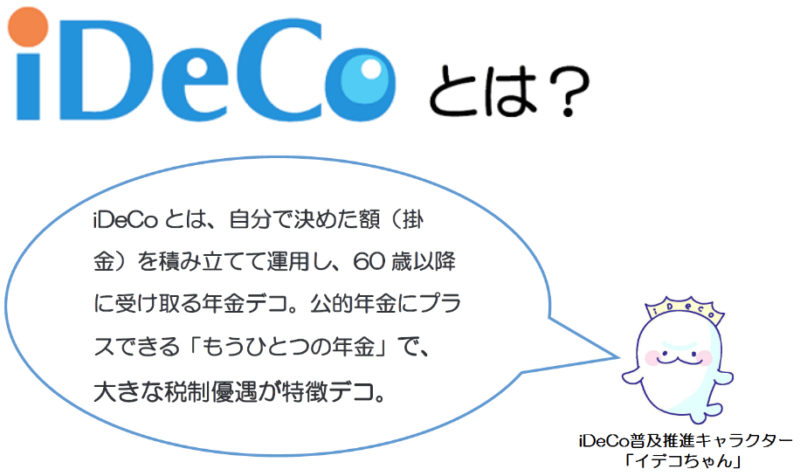
コメント